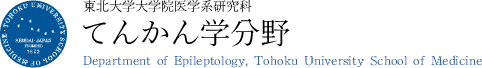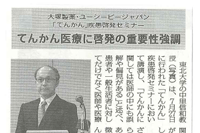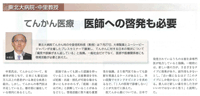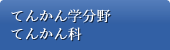- 2010.08.22
-
研究会 JSBET 2010 のホームページがオープンしました
第27回日本脳電磁図トポグラフィ研究会(JSBET 2010)は,2010年11月18日(木)・19日(金),ホテル松島大観荘にて開催されます.
テーマは「夢と理想の神経電磁気生理学」です.多くの皆様のご参加をお待ちしています.
ホームページはこちらから(新しいウィンドウで表示)お入り下さい.
- 2010.08.17
-
Daily Yomiuri Online に掲載されました
2010.8.11の読売新聞「顔」の掲載記事の英語版が,Daily Yomiuri Online に掲載されました.
表題は "IN THE NEWS / Doctor uses university pulpit to tackle prejudice against epilepsy"
格調高い文章で,中里にとっては宝物です.Department of Epileptology と訳してもらえたなら,完璧を超えていました.
- 2010.08.15
-
Medicament News (8/15号)に掲載されました

実地医科のための情報誌「Medicament News」第2024号(2010年8月15日)のコラム「ニュースレーダー」に,中里による7月27日の「てんかんの疾患啓発プレスセミナー」の記事が掲載されました.タイトルは「てんかん治療は医師の連携が重要.適切な薬物治療ならば妊娠も可能」です(記事のPDFはこちら).
一番伝えたかったメッセージのひとつが,次のように,まとめられていました.「治療には専門的な知識が求められる.専門医ですら,誤診は珍しくない.1人の医師の力だけで完治できる疾患ではないことを知って欲しい」
- 2010.08.14
-
雑誌 Clinical Neurophysiology (Elsevier) の Editorial に採用されました.
Nakasato N: Point to point projection from muscle afferent to area 4 cortex. Clin Neurophysiol, in press.
この Editorial で論評したのは,大西秀明先生(新潟医療福祉大学)と亀山茂樹先生(西新潟中央病院)らの研究グループが投稿した論文で,指を動かす筋肉の motor point を刺激した時に大脳の運動野と考えられる部位が反応することを脳磁図でとらえた研究です.刺激した筋肉の部分もピンポイントなら,誘発された脳の部位もピンポイントという,なんとも針穴を縫うようなエレガントな研究論文だと思います.論文は近日中に出版される予定.ちなみに,第一著者の大西先生は,当研究室(運動機能再建学分野)の卒業生です.大西先生,おめでとう!
- 2010.08.09
-
岩沼市でも専門外来が開始となりました.
岩沼市にある「てんかん専門病院ベーテル(新しいウィンドウで表示)」において,東北大学病院てんかん科の神一敬助教と,同脳神経外科の岩崎真樹助教による「てんかん外科専門外来」が開始となります.
当面は,神一敬助教・岩崎真樹助教が,それぞれ月1回で担当します.
- 2010.08.08
-
てんかんセンター(仮称)の記事が河北新報に掲載されました
河北新報の朝刊に,東北大学病院てんかんセンター(仮称)の記事が掲載されました
取材を受けた中里がもっとも伝えたかったメッセージが,一番最後に,うまくまとめられていて感激です(以下).
「専門医が得意とする領域はそれぞれ異なり,1人では誰でも誤診する恐れがある.複数の医師が多角的に症例を検討すれば,患者にとって最善の治療法を見つけることができる」
- 2010.08.06
-
交通事故医療に関する研究助成の対象に選ばれました
社団法人日本損害保険協会が募集していた「交通事故医療特定課題研究助成」(新しいウィンドウで表示)に応募したところ,2010年度の研究助成の対象に選ばれたとの通知が届きました.課題名は「長時間ビデオ脳波モニタリングと脳波・脳磁図の統合解析による外傷性難治性てんかんの病態診断」です.
- 2010.08.04
-
薬局新聞に掲載されました
2010.7.27開催のプレスセミナーの記事が,薬局新聞に掲載されました.
タイトルは,「てんかん医療に啓発の重要性強調」.講演の中からの言葉の抜粋として「てんかんに関しては医師の中にも誤解や偏見がある」というメッセージを伝えてもらえました.
- 2010.08.02
-
1時間外来が始まりました
8月より新しい体制で外来診療が行われます.診察日は原則として,月・火・金の週3日となります.原則,予約制です.
月曜午前は,中里信和が担当し,おもに再来患者さんに充てられます.
火曜午前も,中里信和が担当しますが,予約の新患診療が中心となります.診療時間は通常の外来よりも長めに,1人1時間を確保しています.1時間ずっとお話を聞くわけではありませんが,患者さんの病歴や生活歴,疾患に関する日々の悩みを聞くためにあてたいと考えています.診察の時間,説明の時間,紹介状や検査の予約をする時間を含めて全部で1時間を患者さんお一人に充てたい,という意味です.
診療には原則として事前予約と医師の紹介状が必要です.患者さんの診療結果を患者さん本人の利益とするだけではなく,これまで診療していただいた主治医の先生方に診療情報を還元すべきと考えているためです.つまり,ひとりの患者さんに時間をかけて診察することによって,結果をなるべく多くの患者さんのために役立てたい,という趣旨です.
金曜午前は,神一敬が担当します.こちらも,新患・再来ともに,原則予約制です.
- 2010.08.02
-
Japan Medicine に掲載されました
2010.7.27開催のプレスセミナーの記事が,Japan Medicine に掲載されました.
タイトルは,てんかん医療「医師への啓発も必要」.
・・・専門医であっても診断を間違えるケースがあるとし,早い段階でセカンドオピニオンを求めるなど,「1人の医師で診療しない」ことが大切だと訴えた・・・