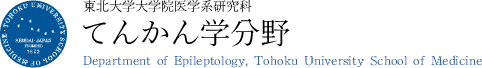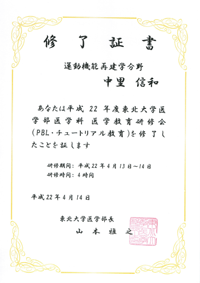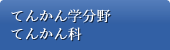- 2010.05.12
-
院内の地域連携カンファランスで,てんかん診療に関する講演を行いました
会の正式名称は,東北大学病院地域連携ランチタイムカンファランス.お弁当を食べながら,病院の地域連携に関する勉強を行う月1回の会です.
演題は「てんかん診療における地域医療連携の意義」.講師の中里にとっては,これから東北大学病院てんかんセンター(仮称)を始動するために,院内の医師やコメディカルにセンターの理念や概念を説明する重要な機会です.しかし,なんとなんと講演の開始直後に,愛機 MacBook Air からプロジェクタへの接続不良が発生.過去何百回と講演してきた中で,初めてのトラブル発生! オリジナルは KeyNoteで作ったので,Windows にも移せません.さいわいなことに,PDF 化したバックアップファイルがあったので,無事に別の Windowsで講演することができました.実際の,てんかん発作のビデオをお見せすることはできませんでしたが,こちらは実演でカバーさせていただきました.
おかげさまで大きな反響を得ることができましたので,また機会をみつけて,プロジェクトの説明をしていく予定です.
さて,この日の夕方,病院のトップからうれしい連絡です.てんかんセンター始動に必要な長時間ビデオ脳波モニタリング用のシステムの年内導入と,これを管理する専任の脳波技師さんの複数名の雇用を認めていただくことができました.
- 2010.05.01
-
加齢医学研究所に新しい講座が誕生しました
東北大学 加齢医学研究所(新しいウィンドウで表示)附属スマート・エイジング国際共同研究センター(新しいウィンドウで表示) に,新講座として「神経電磁気生理学分野」が誕生し,中里信和が教授(兼任)として着任しました.
英文表記は,Department of Electromagnetic Neurophysiology, Smart Ageing International Research Center となります.脳波と脳磁図などの電磁気生理学的手法を駆使し,脳の機能の不思議を解きあかすことを使命とします.
ウエブサイトはまだ建設中です.左のサイドバーの「神経電磁気生理学分野」の下に,活動状況をアップする予定です.
- 2010.04.29
-
日本てんかん学会東北地方会の案内と演題募集が掲載されました
第4回日本てんかん学会東北地方会は,岩手医科大学脳神経外科教授 小笠原邦昭先生を会長として,2010年7月17日(土)午後1時より,仙台市の江陽グランドホテルで開催予定です.演題の締め切りは6月10日正午まで.詳しい案内は,学会ホームページ(新しいウィンドウで表示)まで.PDFのダウンロードは,こちらをクリックして下さい.
- 2010.04.28
-
日本てんかん学会東北地方会のホームページが移動しました
日本てんかん学会東北地方会の事務局が東北大学運動機能再建学分野(てんかん科)に移動したことに伴い,ホームページもこのサイトの中に組込まれました.左のサイドバーの「てんかん学会東北地方会」をクリックしてご覧下さい.
- 2010.04.27
-
広報誌 With に「てんかん科」の紹介が掲載されました
「With」は東北大学病院地域連携センターの広報誌です.第16号(2010年5月号)の INFORMATION「診療科名変更のお知らせ」に「てんかん科」の紹介文が掲載されました
- 2010.04.24
-
てんかん専門外来の当番表を公開しました
東北大学病院てんかんチームでは,将来の東北大学てんかんセンター(仮称)の設立に向けて,関連各科における「てんかん専門外来」と,東北地方の関連拠点病院における「てんかん専門外来」の診療を行っています.
担当する専門医は,中里信和(東北大学病院てんかん科),神一敬(東北大学病院神経内科),岩崎真樹(東北大学病院脳神経外科)の3名で,担当医は今後,徐々に増やしていく予定です.
担当する病院・診療科は,東北大学病院てんかん科(中里信和医師),東北大学病院神経内科(神一敬医師),東北大学病院脳神経外科(岩崎真樹医師)の他,東北地方の関連拠点病院として北から,青森市,盛岡市,一関市,仙台市太白区,郡山市を予定しています.関連拠点病院も,今後徐々に増やしていく予定であり,また診療日も増えていく見込です.
てんかん専門外来の当番表は,左のサイドバーの「てんかん外来のご案内」をクリックしてご覧下さい.グーグル・カレンダー形式です.
- 2010.04.21
-
盛岡市でも,てんかん専門外来が開始となりました
将来予定される東北大学てんかんセンター(仮称)の関連拠点病院として,盛岡市にある岩手県立中央病院において,てんかん専門外来の診療が開始されました.当面は毎月1回,水曜午前を予定しています.近日中に診療日をウエブサイト上に公開する予定です.
- 2010.04.19
-
基礎ゼミ「てんかんという病,その医療を考える」の初日です
全学部の新入生を対象とした2010年度基礎ゼミが開講しました.医学系研究科神経外科学分野助教の岩崎真樹先生が企画したテーマによるもので,初日の今日は20名の受講者がひとりの欠席もなく全員集合しました.医学部はもちろん,工学部や文学部に至るまで多彩なメンバーです.受講者全員と教官(岩崎・中里・神・大沢)の自己紹介のあと,てんかんに関するアンケート調査用紙が配布され,「あなたは,てんかんをどう理解していましたか?」というコンセプトでの質問に,受講前に答えていただきました.集計結果が楽しみです.
それにしても,新入生諸君の初々しいこと! 常識に縛られない若い人たちの意見で,われわれの包括的てんかんプロジェクトを立ち上げるための新しいヒントが得られるのではないかと期待しています.
- 2010.04.14
-
遅ればせながら,チュートリアル教育を受けてきました
昨日と今日の二日間にわたり,中里信和はPBL・チュートリアル教育なるものを受講し,終了証書をもらってきました.通常は大学教官としてのキャリア上,もっと早い段階で受講するものらしいのですが,10年ぶりで大学に戻った私は興味半分でノコノコでかけて行ったという次第.これまでの医学教育は,教官中心で生徒に対して一方向的な講義を行うスタイルが中心.これに対してチュートリアル教育では,生徒が数人でグループを作り,テーマとなる症例のシナリオを読みながら生徒同士で解決策を話し合う,というスタイルです.
参加者は実際に4グループに分かれて,学生時代に戻った気分での討論を行いました.私には,とても新鮮でした.ついつい専門領域のことを考えてしまい,ひょっとすると,てんかん患者さんの病歴を聴取する専門医の訓練に,このシステムが使えないかと思った次第.指導にあたってくれた医学教育推進センターの金塚完先生,石井誠一先生,亀岡淳一先生,ありがとうございました.こういうのが,大学らしい「知的サロン」なのでしょうね.
- 2010.04.10
-
郡山市でも,てんかん専門外来が開始となりました
東北大学てんかんセンターの設立に向け,東北各地からの難治性てんかん症例を集める目的で,関連拠点病院が設置されることになっています.その最初の病院として,郡山市にある総合南東北病院において,本日,診療が開始されました.当面,てんかん専門外来は隔週の土曜午前を予定しています.近日中に診療日をウエブサイト上に公開する予定です.