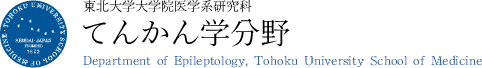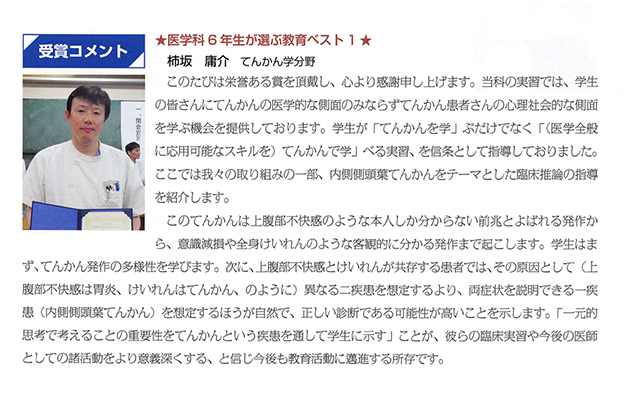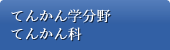- 2019.10.9
-
日本てんかん協会のプレスセミナーで中里教授が脳磁図を取り上げました
てんかん月間を記念して、毎年10月には日本てんかん協会のプレスセミナーが開催されています。この日のプレスセミナーで、中里教授は脳磁図検査の話題を取りあげました。脳磁図は脳が発生する微弱な磁界を測定する検査法です。脳波に比べて空間的な精度が高いために、てんかんの術前診断には欠かせない検査です。ところが最近、脳磁計を保有する施設で、次々と脳磁図検査ができなくなっています。その背景には、国際的なヘリウム不足の問題があります。さらには脳磁図検査への診療報酬があまりにも低く、病院としては採算が取れないため検査を中止せざるをえない状況に追い込まれているのです。講演の中で中里教授は、脳磁図検査の重要性を国民に正しく理解してもらい、相応の診療報酬がもらえるようになることが大切だと強調しました。
- 2019.10.1
-
東北大学病院遠隔医療推進ワーキング・グループのキックオフ・ミーティングが開催されました
本日、東北大学病院第一会議室において遠隔医療推進WG キックオフミーティングを開催されました。冒頭、冨永悌二病院長から「東北地方には医療課題が集積しており、この改善の一助として遠隔医療の推進を図りたい」との挨拶がありました。次いで、中里病院長特別補佐(遠隔医療担当)から、「遠隔医療の天地人」と題して、日本における遠隔医療の現状、てんかん科における遠隔医療への取り組み、海外の事例の紹介がありました。発表後のフリーディスカッションでは、満員の会場内からの活発な発言や意見交換だけでなく、遠隔地からの参加者による発言や情報提供が行われ、盛況のうちに閉会となりました。詳細は東北大学病院のホームページに写真入りで掲載されています。今後このワーキンググループは月一回のペースで開催される予定です。
- 2019.10.1
-
ミュンスター応用科学大学修士課程に在籍中の Fabian Kaiser 君が特別研究学生として来日しました
Fabian Kaiser 君はドイツにあるミュンスター応用科学大学修士課程に在籍中です.すでに脳磁図の信号源解析に関する研究を行っていますが,脳磁図の生理学研究および臨床への応用を学ぶべく約1年の予定で来日しました.日本語の日常会話も達者です(詳しくはこちら).
- 2019.9.13
-
神准教授が国際臨床脳磁図学会の理事に選出されました
9月11日より、カナダのトロントにて第7回国際臨床脳磁図学会が開催されました。先日の選挙において、神一敬准教授が次期4年間の理事に選出されたことが、この日の理事会において発表されました。本学会は脳磁図の臨床応用を推進するために2007年に発足した国際学会であり、初代理事長には中里教授が着任しました。その後、1年おきに学術大会が開催され現在に至っています。
- 2019.8.30
-
協同研究者の柿沼先生が Falling Walls Lab Sendai 2019で第一位!
Falling Walls Labとはベルリンの壁の崩壊(1989年)から30年になることを記念して、さまざまな分野で活躍している若手研究者が、自分の研究内容を3分にまとめて発表する世界的なコンテストです。高次機能障害学分野の柿沼一雄先生は、てんかんの術前診断として実施している超選択的ワダテストを用いた脳機能マッピングについて発表し、見事、第一位を受賞しました(https://www.tfc.tohoku.ac.jp/fwls/report.html)。柿沼先生は11月8〜9日にベルリンで開催される本選(https://falling-walls.com/lab/apply/)への参加が決定しました。柿沼先生、おめでとうございます。
- 2019.7.27
-
中里教授の還暦を祝う会が開催されました
この日は中里教授の満60歳の誕生日です.毎月1回,土曜日に開催される東北大学てんかん症例検討会のあと,サプライズで花束が渡され,遠隔会議システムからの参加者からもお祝いの言葉が述べられました.このあと,サプライズ満載の祝賀会も開催され,遠路からの研究室卒業生も加わって盛代なパーティーとなりました.中里教授の感激の言葉「まるで生前葬です.ありがとうございました.生まれ変わったつもりで頑張ります」.これに対して神准教授の言葉「お願いですから,これ以上,あまり頑張らないで下さい」.



- 2019.7.11
-
フィリピン大学の Franchesca Gabriel 先生が客員研究員として来日しました
Franchesca Gabriel 先生はフィリピン共和国の首都マニラにあるフィリピン大学を卒業し,すでに神経内科医として専門医を取得しています.このたび日本てんかん学会と日本てんかん治療研究振興財団のスカラーシップをもらい,約1年の予定で,てんかん学について学ぶ予定です.愛称はチェスカ先生です(詳しくはこちら).
- 2019.6.21
-
河北新報に神一敬准教授の記事「てんかんの正しい理解を」が掲載されました
河北新報では連載記事の「気になる症状すっきり診断 東北大学病院専門ドクターに聞く」が第1・第3金曜日に掲載されています。今回は、てんかん科・てんかん学分野の神一敬准教授の記事「てんかんの正しい理解を」が掲載されました。
記事の詳細は、こちら - 2019.5.21
-
柿坂庸介講師が2度目のベストティーチャー賞を受賞しました
2019年5月21日に開催された東北大学医学部教室員会総会において、柿坂庸介講師が「医学科6年生が選ぶ教育ベスト1」に選ばれました。今回の受賞は柿坂先生にとっては2度目になります。柿坂先生、おめでとうございます! (添付記事は「教室員だより25巻2号(2019)」より)
- 2019.4.1
-
寄附講座が共同研究講座に生まれ変わりました
株式会社リコーからの寄附によって2017年2月に発足した神経電磁気生理学寄附講座は、2019年4月より新たに「電磁気神経生理学共同研究講座(リコー)」として生まれ変わります。これによって、企業と大学とが対等な立場で協力しあい、電磁気神経生理学領域のさらなる発展を目指します。