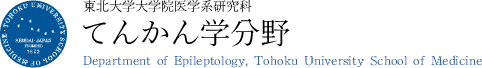2013年2月13日からは、てんかん学分野の中里信和教授が執筆を担当しています。
- 第20回(2013年6月26日河北新報朝刊)てんかん診療理想形/来た、見た、勝った
- 第19回(2013年6月19日河北新報朝刊)てんかんと脳梁離断術/乳幼児は発作軽減も
- 第18回(2013年6月12日河北新報朝刊)ツイッターの光と影/正義感だけ独り歩き
- 第17回(2013年6月5日河北新報朝刊)てんかんとツイッター/情報伝達、うってつけ
- 第16回(2013年5月29日河北新報朝刊)てんかんへの誤解と偏見/解消へ啓発が不可欠
- 第15回(2013年5月22日河北新報朝刊)大脳半球を取る手術/神経だけを切り離す
- 第14回(2013年5月15日河北新報朝刊)てんかんを手術で治す/電気刺激で部位特定
- 第13回(2013年5月8日河北新報朝刊)抗てんかん薬を選ぶ/検査通じ副作用軽減
- 第12回(2013年5月1日河北新報朝刊)てんかんと妊娠/正しく服薬無事出産
- 第11回(2013年4月24日河北新報朝刊)てんかんと運転/感情に走らず理解を
- 第10回(2013年4月17日河北新報朝刊)遠隔てんかん外来/地域医療の切り札に
- 第9回(2013年4月10日河北新報朝刊)新時代の海外留学/検査技術普及への派遣
- 第8回(2013年4月3日河北新報朝刊)脳磁図/「脱超伝導」計測が夢
- 第7回(2013年3月27日河北新報朝刊)てんかん発作をとらえる/脳波の連続測定 有効
- 第6回(2013年3月20日河北新報朝刊)パープルデー/特別授業契機 世界に
- 第5回(2013年3月13日河北新報朝刊)震災時のてんかん患者/障害克服 支援で活躍
- 第4回(2013年3月06日河北新報朝刊)お湯てんかん/強い皮膚感覚 脳刺激
- 第3回(2013年2月27日河北新報朝刊)てんかん新患外来/長時間の問診が大切
- 第2回(2013年2月20日河北新報朝刊)大学病院てんかん科/誤解や偏見 解消急務
- 第1回(2013年2月13日河北新報朝刊)てんかん学/先端研究 次々と成果
第20回(2013年6月26日河北新報朝刊)てんかん診療理想形/来た、見た、勝った
てんかん診療の理想は「来た、見た、勝った」だ。共和制ローマの将軍ユリウス・カエサルが、戦勝を伝える手紙に「カエサルが戦地に来た、敵を見た、戦いに勝った」の意で使った言葉であり、簡潔明瞭なラテン語の理想形とされる。カエサルにはてんかんがあった。それはさておき、主語を「患者」に置き換えてみよう。
てんかんに「勝った」と言えるのは、発作ゼロ、悩みゼロ、不安ゼロの達成だ。そのためには発作を「見た」が大切だ。以前紹介したビデオ脳波モニタリング検査によって発作を確認できれば、薬や手術などの最適な治療法の選択が可能だ。患者も自身の安全確保に本気で取り組むようになる。
何より大切なのは、患者が「来た」だ。最新医療の存在を知らずに外来診療を漫然と続けてしまうことを、私は「無限ループ」と呼んでいる。私自身の反省を込めてだが、一人で診療せずに、なるべく早く入院検査を受けさせたいと思う。
てんかんや神経疾患の専門医を自負する医師ほど無限ループからの脱出に手間取る。患者が自分で情報を集めた上で、主治医を説得して専門医に紹介してもらった例も少なくない。
「来た、見た、勝った」の達成には、教育と啓発があらゆる場面で必要だ。医師や医療者だけではない。全ての人たちに対してだ。本欄の連載も、ネットを通じて全国に配信されており、大変にありがたい。
てんかん手術と脳機能研究で有名な故ワイルダー・ペンフィールド先生の自叙伝には「NO MAN ALONE」のタイトルが付く。「一人では何事も達成できない」の意だ。診療ネットワークづくりに励むことを誓い、筆をおく。
第19回(2013年6月19日河北新報朝刊)てんかんと脳梁離断術/乳幼児は発作軽減も
脳は「ケーブル」の塊だ。ヒトの大脳には100億個以上の神経細胞があり、神経細胞同士を連絡するためのケーブルはさらに多い。
ケーブルの束として一番太いのは脳梁(のうりょう)だ。建物の梁(はり)と同じく、左右の大脳半球を水平に連結している。断面は人さし指の大きさで、その中を3億本ほどのケーブルが走る。
脳梁は女性の方が太い。脳全体は男性の方が大きいので、不思議で面白い事実だと思う。
ひょっとして、女性はバランス思考が得意で、平時の生存に適しているのだろうか。男性は左右の脳が独立し、危機を打破するとっぴなアイデアを生み出すのに適しているのだろうか。これはあくまでも私の勝手な推論なので、本気で信じないようにしていただきたい。
てんかんの中には、脳梁を介して左右の脳が繰り返し刺激しあい、異常に興奮するタイプもある。乳幼児の場合には、脳梁を手術で切り離すと発作が軽くなり、時には発作が消える場合もある。
この脳梁離断術では、左右の脳が完全に独立するのは切除の最後の瞬間だ。少しでも脳梁が残っていると、左右の同期はしぶとく残る。
成人では通常、脳梁の離断は行えない。左右の大脳が完全に独立すると、いろいろと不都合が起きるからだ。例えば、目隠しをしながら左手で触った物品を、言葉では表現できなくなる。左手からの情報は右の大脳に届くが、言葉を操る左の大脳には脳梁がないため、情報を伝えられないのだ。
てんかんの治療法の開発と脳の働きの基礎研究は、このように切り離せない関係にある。
第18回(2013年6月12日河北新報朝刊)ツイッターの光と影/正義感だけ独り歩き
ツイッターを含めたソーシャルメディアには光と影がある。
京都市で昨年4月、車の暴走により通行人19人が死傷する事故があった。運転し死亡した男性に、てんかんの持病があったことが大きく報道された。
事故の直後、ツイッターでのコメントが爆発的に増えた。「てんかん患者の運転を禁止せよ」が大半だった。「患者サイドに立つのは、遺族の気持ちを無視している」という激しい意見もあった。
患者や家族が反論できる状況ではなかった。ここは私の仕事だと覚悟を決めた。「冷静に。あなたも明日、てんかんになりえます。自分のことだと思って考えてください。てんかんは個人差が大きい疾患です。発作が消え、安全に運転している方も多いのです。病名だけで差別しないように」
当時900人だったフォロワーは3日で倍増した。ツイートの往復も2000を超えた。私を「人殺し」と罵倒した人も、翌日には「誤解していました」と謝った。
こうしたやりとりを、ツイッターを通じて多くの患者や家族が見ていた。「事故後、周囲の目が怖くて、家に隠れていました」という患者は「先生のコメントに励まされました」とツイートしてくれた。
フォロワーにはメディア関係者もいて、いくつかの取材を受けた。その後の記事や放送内容には、てんかんへの偏見に対する配慮が感じられた。
てんかんへの偏見は誰もが持ちうる。悪意からではない。知識が不足した状態で、正義感だけが独り歩きするのだ。解決には万人への啓発があるのみだ。「影」に注意しつつも、ツイッターの「光」に期待する理由はそこにある。
第17回(2013年6月5日河北新報朝刊)てんかんとツイッター/情報伝達、うってつけ
前回、てんかんへの偏見を取り除くには啓発活動が重要だと指摘した。そのためにうってつけの手段にツイッターがある。
ソーシャルメディアの一つで、既存のメディアでは伝えきれない情報伝達手段として多くの人が毎日利用している。貴重な情報が届いたり、緊急のコメントを出したいと考えたりした時、一瞬で多くの人たちにそのメッセージを伝えられる。
ツイッターの読者はフォロワーという。私の場合は約3000人。患者や家族、医師、学生に加え、マスコミや政府、自治体職員もいる。ツイート(つぶやき)は140文字以内。メッセージに共感したフォロワーは別のフォロワーに転送する。
ツイッターでの個別の医療相談は違法だが、一般的な情報は伝えることができる。
「発作の残存や悩みがあれば、主治医にお願いして専門医に相談すべきだ」とのツイートを読んだ30代の男性から「毎週発作がありますが、専門医の街まで3時間もかかるので無理」と返信があった。「地元の主治医と専門医に、連携をお願いすれば?」と私。1年後「専門医を受診したら、側頭葉てんかんの手術を勧められました。おかげで発作も消えています」との連絡があった。
ある20代の女性は「私の先生の出す薬は強過ぎ。内緒ですが、朝の薬は飲んでません」。医師と患者との信頼関係の構築は難しい。「強いと感じる気持ちを正直に主治医に伝えたら?」と私。後日「新しい薬に変更で、副作用も消えました!」と喜びの返信が続いた。
政治家の失言など、ツイッターには難しい点も多い。気を付けなければと思いつつも、今すぐ伝えなければという気持ちが私の背中を後押しする。
第16回(2013年5月29日河北新報朝刊)てんかんへの誤解と偏見/解消へ啓発が不可欠
てんかんへの誤解は、古今東西、数多くある。
全身けいれんの対処方として、特に有名な誤解は「舌をかまないように何かを歯にくわえさせる」だ。一般の方だけでなく、医師でも誤解している人が少なくない。何かを口に入れようとして歯が折れたり、窒息させたりする危険もある。発作の時には、落ち着いて周囲の安全を確保するだけで良い。
日本ではかつて、てんかんの発作を止めるため、「頭に草履を載せなさい」という迷信があった。ネパールでも、発作で倒れた患者の頭を足で踏みつける誤った対処法が残っているそうだ。
コンピューターでの作業を長時間行うことは、てんかんの原因になると誤解している方もいる。てんかんの人は、そうでない人に比べて知的能力が低いと誤解している人もいる。脳の別の病気が合併しない限り、そのようなことはないのだが。
てんかんは遺伝病との誤解は、医療関係者さえ持っていることがある。伝染病だと誤解する人もいるから驚きだ。中東のクウェートでは、悪魔に取りつかれた病、とする迷信もある。
世界中どこでも、てんかん患者の多くが疾患名を隠そうとする。誤解や偏見から自分を守るため、やむにやまれずなのだ。
「脳があるなら、あなたも明日、てんかんになりえます」
これは、海外で使われている、てんかん啓発キャンペーンの文句だ。てんかん患者を人ごととして差別するのではなく、誰でもいつでも起こることだと考えれば、誤解や偏見は減るのではないだろうか。
偏見は無知から始まる。それをなくすには、教育と啓発活動を根気強く続けるしかない。
第15回(2013年5月22日河北新報朝刊)大脳半球を取る手術/神経だけを切り離す
前回は1立方センチに満たない脳の切除で、てんかんが治った例を紹介した。今回は大きな手術を紹介する。
ヒトの脳を特徴づけるのは進化の過程で発達した大脳だ。大脳は出生後も数年間成長し続ける。大きさだけでなく、乳幼児期は神経回路の発達も著しい。
その大脳の片側だけが異常に肥大する病気が「片側巨脳症」だ。
A君は生後3週間目から、右の顔面と手足のけいれん発作が止まらなくなった。脳波では左の大脳の興奮が持続している。2歳になるころには右半身の脱力も出現し、知的な遅れも目立つようになった。左の片側巨脳症だった。
薬だけでは病気の進行は抑えられない。肥大した左大脳に加えて、正常だった右大脳にまで障害が及ぶ。いずれ寝たきりとなり食事の摂取は困難となる。合併症で死亡する危険も高い。この病気には「破局てんかん」という別名すらある。
肥大する大脳を取り除く手術は1950年代に始まった。現在の「大脳半球離断術」では脳組織は血管と共に残し、神経連絡だけを切り離す高等戦術を採用し、合併症を減らしている。
A君も3歳で手術に踏み切った。1年後、彼が住む北海道の病院から様子を知らせるビデオが届いた。右半身のまひは残っているものの、元気に廊下を走り、言葉も話せるようになった。切り離された左大脳の働きを右大脳が代償しているのだ。
大手術だが、早いほど良いので、生後3カ月で実施することもある。小児科神経科医や脳神経外科医などとの連携が大切だ。昨年、東京で開催された「破局てんかん」の国際会議では、「もう破局とは言わせない」と皆で誓った。
第14回(2013年5月15日河北新報朝刊)てんかんを手術で治す/電気刺激で部位特定
てんかん外科の父と呼ばれるイギリス人医師ビクター・ホースレイは19世紀末、脳の一部を切除する治療法と、脳を電気で刺激する検査法を相次いで開発した。
前回、てんかん患者の6割以上が薬で発作を抑えることを紹介した。薬が無効の場合は、手術で治せる場合も少なくない。ただし、誰にどんな手術を行えばよいのかは、専門施設で多くの検査を経なければ判断することができない。
腫瘍や血管奇形などの脳疾患は、磁気共鳴画像装置(MRI)などの画像診断で見つけることができる。しかし、てんかんでは一見すると正常な部位に原因が隠されている。
脳の部位ごとの機能も画像診断だけでは分からない。切除したい部位と、脳の大切な場所が近接している時には、ホースレイのように電気刺激の検査が必要になる。
最近の医学の進歩は目覚ましい。手術の前に、てんかんの原因部位や脳の機能部位を絞り込む安全な検査法が次々と開発された。私が20年以上前から取り組む脳磁図もその一つだ。
30代の主婦Aさんは、左足の激痛を伴うけいれんを毎日10回も繰り返していた。薬は無効で手術しか治療法はない。しかし脳の切除では左下肢がまひする危険があった。
MRIの異常は微妙であり、手術は決断できなかった。しかし脳磁図が捉えた異常活動はその場所に一致した。最小限の電極を埋め込んで刺激試験を行った結果、下肢を動かす正常部位と、てんかんの原因部位とが数ミリの距離で識別できた。
最終的に切除した脳の大きさは1立方センチに満たなかった。まひはなく発作も消え、Aさんの生活は元通りとなった。
第13回(2013年5月8日河北新報朝刊)抗てんかん薬を選ぶ/検査通じ副作用軽減
薬で発作が消えたものの、「パターが入らず、ゴルフが下手になった」と訴える男性患者がいた。検査異常は認められない。「発作が消えたのだから、ゴルフの件は我慢できませんか」と諭すと、「社長として社員とのゴルフに負けたくない」と反論された。
よく使われる抗てんかん薬は現在20種類ほど。病型ごとに推奨薬は異なり、個人差もあるので、薬剤の選択は常に悩む。最初の薬で発作が消える人は約半数。第二、第三の薬も合わせて、6割以上で発作は抑制される。ただし成人の場合、薬は生涯継続するのが原則なため、副作用の少ない薬が望まれるのは当然だ。
薬を開始した直後は特に注意が必要だ。発疹、発熱、精神症状などで、薬を中止しなければならない場合もある。
投与量が増えると、それに合わせて強くなる副作用もある。古い薬では眠気や目まい、ふらつきなどの症状が多い。抑うつ的になり、食欲が低下し、体重が減る人もいる。このような場合、生活の質を保つためにも薬を減らすか中止しなければならない。
長期の服用では、薬によって、肝臓への障害や骨粗しょう症、不妊など、さまざまな合併症が生じる場合がある。はじめは自覚症状が少ないので、前もってしかるべき検査を行うことも大切だ。
最近は次々と新しい薬が使えるようになってきた。発作を抑える力もさることながら、長期の副作用が小さいことも患者にとって朗報だ。
冒頭の社長も、新薬に変更して「発作ゼロ、副作用ゼロ」を達成できた。ゴルフのスコアは元に戻り、「面目を保っている」そうだ。
第12回(2013年5月1日河北新報朝刊)てんかんと妊娠/正しく服薬無事出産
患者に説明する際、「てんかんですね」で言葉を止めてはいけない。それでは説明不足だ。てんかんの分類や原因、治療法などを伝えた上で、患者と家族が前向きに考えられるように十分な説明をすることが必要だ。
「発作を早くゼロにして、2年後には運転免許を取るための診断書を書きたいですね」というのは私がよく使うせりふだ。「赤ちゃんが産まれたら見せに来て」と言うと、同席する両親が「子どもは無理と諦めていました」と泣きだすこともある。
てんかんがある女性や抗てんかん薬を服用する女性から生まれる赤ちゃんに、何らかの障害のある危険性はゼロではない。しかし、注意点を守れば通常の妊娠と比べてもリスクの差はわずかだ。薬の種類を絞り、投与量も最少量にして、妊娠前から葉酸を補充しておく。妊娠中も薬の量はそのままが原則だ。出産後も服薬しながら母乳を与えても構わないことが多い。
30代のAさんは下肢から全身に波及するけいれん発作を毎月繰り返していた。10年の間に薬は次々と追加され、私が診察した時には3剤を併用していた。しかも、赤ちゃんに影響が出る危険性が大きい組み合わせだった。発作を止めるためだけでなく、妊娠への影響も考え、新薬へ切り替えることを勧めた。
「結婚も妊娠も考えていませんから」と、本人は既に覚悟していた様子だった。しかし、新薬が合ってくれて発作は消えた。今までの薬の服用も中止することができた。
3カ月後、「妊娠しました。結婚も」と言われ、吉報の早さに驚いた。無事に出産後、産科病棟に往診すると、夫に「カメラ持ってきて。先生と写真よ」。Aさんと夫を見て私の涙腺も緩みっぱなしになった。
第11回(2013年4月24日河北新報朝刊)てんかんと運転/感情に走らず理解を
てんかん関連の交通事故が起こると、病名だけで運転を禁止すべきだとの極論が飛び出す。てんかん発作が2年以上ない場合など、多くの患者は運転が許可されているのだが、感情的な意見が多いのは残念だ。この問題を科学的に分析してみたい。
安全管理学では「絶対安全は存在しない」が大前提の考え方だ。危険は常にあり、これを最少化するのがリスク管理となる。運転免許の場合は、絶対安全な運転者はおらず、リスクが低い人に免許証が交付されると考えるのが合理的だ。
てんかん発作が1年ない人の発作の再発率はきわめて低い。一般の人が事故を起こす危険率と差がないため、病名だけでの絶対禁止は理不尽だろう。
もちろん、てんかん発作が残っている人の運転は特殊な場合を除いて禁止されている。残念ながら、法律や制度を詳しく説明しても運転をやめない患者はいる。悪気があってのことではない。自分の発作を自分ではよく知らないため、危険に気づかないのだ。
以前紹介したビデオ脳波モニタリング検査は生活指導にも役立つ。発作のビデオを本人に見せると、誰もが発作の危険性を理解する。隠れて運転していたことを告白し、以降の運転をやめると誓った人もいる。
イソップ寓話(ぐうわ)の「北風と太陽」に例えるならば、法律などで縛るのは北風かもしれない。疾患への理解を深める教育は太陽であり、危険を減らす王道だ。
一方で、てんかんの治療が成功し、安全に運転を続けている人が多数いることも社会には理解してもらいたい。疾患名だけで差別する人にも、太陽のような啓発活動が必要だと考えている。
第10回(2013年4月17日河北新報朝刊)遠隔てんかん外来/地域医療の切り札に
笑顔であいさつを交わし、自己紹介をしてから、患者の氏名を確認する。てんかん外来の始まりだ。ただし、いつもと違うことがある。私が東北大学の自室にいるのに対し、患者は気仙沼市立病院の診察室にいる。ハイビジョンカメラとインターネットによる遠隔会議システムを使っているのだ。
装置は、友人で米・アーカンソー大学の産婦人科医、L先生が東日本大震災への支援として送ってくれた。2005年の巨大ハリケーンで、彼の住む米国南部も大きな被害を受けた。アーカンソー大はハリケーンの被災地支援として遠隔医療の普及に力を入れた。産婦人科の専門医がカバーできない地域も、このシステムがあれば妊婦の定期健診が可能だ。皮膚科、眼科の診察や脳梗塞の救急治療にも使われているという。
以前も紹介したように、てんかん診療では問診が何よりも大切だ。ハイビジョンの高画質によって、違和感なく普段通りの診療が可能となった。テレビの画面を通して会話をするうちに、患者と家族が徐々にリラックスしてくるのを実感できる。
このシステムには思わぬメリットがあった。気仙沼市立病院脳神経外科のN先生や研修医らが、てんかん診療のこつを会得してきたことだ。
現在、東北大学と宮城県は、遠隔医療をさらに普及させる計画を持っている。遠隔医療は近い将来、地域医療の切り札として、全ての病院に不可欠の道具になるだろう。
気仙沼と仙台を往復する時間が節約できたのは喜ばしい。だが困ったことがある。以前は気仙沼で、N先生と一緒に魚や酒を楽しむ機会があった。遠隔会議システムを少しうらめしく感じるこのごろである。
第9回(2013年4月10日河北新報朝刊)新時代の海外留学/検査技術普及への派遣
遣隋使や遣唐使の時代から、留学は外国から学術や技芸を学ぶことが目的とされていた。最近では先進国から途上国へ留学する例もある。グローバル化により、留学のスタイルは相互的で多元的になっている。
前回紹介した脳磁図検査は、欧米よりも日本での普及の方が早かった。だが日本から素晴らしい成果を発表しても、検査の装置を持たない研究者にとっては絵に描いた餅も同然だった。脳磁図の素晴らしさを、どうすれば世界に広めることができるか、私は随分と焦っていた。
1999年、チェコで開催された国際会議で講演中、聴衆の中にL先生の姿を見つけた。彼の率いる米・クリーブランドクリニックのチームは全米一のてんかんセンターとして有名だ。
もしそこに脳磁計が導入されれば、脳磁図検査の評価は一気に高まる。今がチャンスだと考えた私は、講演終了後にL先生を探し出した。「脳磁計を導入しませんか」と切り出して、「装置を動かす仕事は私の仲間にやらせてください」と続けた。翌年、てんかんに関する講演をお願いすべくL先生を仙台に招待したときも、脳磁図を宣伝した。やがて念願がかない、クリーブランドクリニックに脳磁計が導入されることになった。
その後、約10年にわたり、東北大学病院の3人の若い医師が相次いで渡米した。仙台式の脳磁図検査の技術を米国に教えるのが目的だった。米国での脳磁図検査に対する評価はその後、高まり、脳磁計の普及台数も現在は日本を超える勢いだ。
その3人の医師たちは、4月からそろって東北大学病院で働いている。彼らの米国みやげは、米国方式の優れたてんかん診療システムだ。
第8回(2013年4月3日河北新報朝刊)脳磁図/「脱超伝導」計測が夢
高校生のころから物理が好きだった。将来は物理学を駆使した脳の研究テーマを見つけたいと考えていた。
初めて日本てんかん学会に参加したとき、運命の出会いがあった。書籍コーナーで手にした本の最終章には「てんかん患者には新しい診断技術による明るい未来がある」というタイトルが付けられていた。脳から発生する弱い磁場(脳磁図)を「超伝導量子干渉素子」で計測し、てんかんの診断に役立てる話が紹介されていた。地球の磁場の100億分の1と微弱だが、私の夢そのものだと感じた。
若くて思い込みの激しかった私は脳神経外科医としての研修を後回しにした。東北大理学部や茨城県つくば市にあった電子技術総合研究所に通って「押し掛け研究者」となった。
当時の脳磁計は臨床応用には程遠いものだった。外部の磁気雑音を避けるため、測定開始は深夜の午前0時と決まっていた。1チャンネルで頭部全体を調べるため、1人の被験者で何週間もかけて測定した。
研究開始から約10年後、患者に使える脳磁計を入手した。脳磁図を使うと、さまざまな脳の活動部位をミリメートル単位で推定できる。てんかんの診断にも有用な検査であり、現在は保険診療に組み入れられている。
2007年、第1回国際臨床脳磁図学会を宮城県松島町で開くことができた。感無量だった。世界中から集まった参加者には、医師だけでなく理工系の研究者も多かった。
私の次の夢は、超伝導を使わずに脳磁図を計測する方法を開発することだ。もちろん今回も理工系の研究者と一緒に夢の計画を練っている。そして近いうちに、若くて思い込みの激しい研究者を仲間に加えたいものだ。
第7回(2013年3月27日河北新報朝刊)てんかん発作をとらえる/脳波の連続測定 有効
外来診察と脳波検査では、てんかん診断が難しい場合がある。このようなときは入院して行うビデオ脳波モニタリング検査が有効だ。80時間の連続測定で発作の瞬間をとらえるのだ。
Aさんは30代の設計士。1日5回も倒れ、会社を辞めざるを得なかった。発作の瞬間、右の手足は屈曲し、左の手足は伸展しながら、体はベッドの左側に激しく跳んだ。運動機能を統括する脳の補足運動野に原因があることが、ビデオから特定できた。その後、手術で発作はなくなった。
Bさんは20代女性。けいれんで何度も救急搬送されていた。検査入院中、発作が始まった。ベッドから転落して、床の上で3分以上も手足を大きく震わせた。しかしその間、脳波に異常は見られなかった。
この発作は現実に適応できない心理状態が無意識に生み出すもので、てんかんではなかった。精神科医のカウンセリングによって発作は消えた。
Cさんは30代の男性。突然、一点を見つめたまま、口をモグモグ動かす発作がビデオに記録された。本人は発作を全く自覚していなかった。脳波と合わせて、記憶や意識をつかさどる側頭葉のてんかんと判明した。薬の変更で発作はなくなり、2年半後に運転免許も交付された。
医師が外来で発作に遭遇するのはまれだし、発作を見ても同時に脳波をとっていないと診断は難しい。入院検査なら発作をとらえるチャンスは増える。もっと多くの患者に、この検査を役立てたい。
80時間分の脳波はパソコン画面で3万ページにも及ぶ。患者の人生にかかわる検査なので、判読は機械には任せられない。全て脳波技師や医師が自分の目で確認しているのだ。
第6回(2013年3月20日河北新報朝刊)パープルデー/特別授業契機 世界に
3月26日は「パープルデー」。てんかんを正しく理解してもらうためのキャンペーンの一つで、この日に紫色の物を身に着けようと名付けられた。欧米では紫は「孤独」を意味する。てんかんと診断されても孤立しないように、との趣旨だ。
「私はキャシディ、9歳です」で始まるパープルデーのホームページには「てんかんがありますが、普通に暮らせます。てんかんで独りぼっちだと感じている人がいたら、ここに仲間がいることを知って」とある。
カナダに住むキャシディ・メイガンの両親は、てんかんであることを学校で隠すよう娘に勧めた。だが彼女は公表する方が友達が助けてくれると考えた。2008年3月26日、キャシディの担任の先生は、てんかんを理解するための特別授業を行った。その話を地元のてんかん協会が取り上げたことを契機に世界中に広がる活動となった。
てんかんの啓発活動をしている人にオーストラリアのウォーリー・ルイス氏もいる。ラグビー界のスターだった彼はある日、テレビカメラの前でてんかんの発作を起こして意識を失った。手術で完治した彼は、てんかんへの偏見を取り除くために国内外で講演をしている。
てんかんへの偏見をなくすには正しい知識の普及が唯一の解決策だ。だが人によって症状が異なり複雑であることから、テレビ番組や新聞記事で一度に全てを説明することは困難だ。
難しいことを時間をかけてでも分かりやすく説明することもてんかん診療に携わる者の任務である。それには、てんかんに関する社会問題について広く注目してもらうことが先決だ。
26日、われわれてんかん科のスタッフは、紫色の物を一つ身に着けて診療に当たる。
第5回(2013年3月13日河北新報朝刊)震災時のてんかん患者/障害克服 支援で活躍
東日本大震災から2年がたった。抗てんかん薬を被災地に届けた活動や、現地で医療活動を展開した医療関係者の話、そして患者の悩みに電話相談で応じた支援団体の活動に関しては既に報道されている。今回は、てんかんがありながらも支援活動などに活躍した方たちがいたことを紹介したい。
Aさんは津波の被災地に住む70代女性。物忘れがひどく得意の料理もできなくなって認知症と診断された。数年後、無意識動作や全身けいれんの発作を繰り返すようになり、私が診察した。側頭葉てんかんだった。記憶障害は続いていたが発作は新しい薬で消えたので、地元の病院に継続治療をお願いした。
震災の1年後、消息が分からなかったAさんに会えた。娘さんによると「母は震災直後、炊き出しをして毎日避難所に届けた」という。認知症かと諦めていた記憶障害は、てんかんの二次症状であり、完治していたのだ。得意の料理でみんなを助けたこととともにうれしく、目頭が熱くなった。
Bさんは電話会社に勤める男性技術者。てんかん発作は薬で消えている。震災当日は内陸部で仕事中だったが、「被災地では携帯電話がかかりにくいはず」と沿岸部に移動。移動基地局を設置し、携帯電話を現地の病院スタッフに配った。全て独自の判断だった。
病院関係者から「おかげで支援を求める緊急通信ができた。まさに英雄」と聞かされていたが、その本人に外来で再会できたことに私は感激した。
てんかんは疾患や障害としてのみとらえられがちだが、てんかんがありながらも歴史に残る仕事をした人は大勢いる。今回の震災でも、多くのヒーローが誕生していたのだ。
第4回(2013年3月6日河北新報朝刊)お湯てんかん/強い皮膚感覚 脳刺激
てんかんの発作はきっかけなしに始まるが、例外として「反射てんかん」がある。その代表例が視覚刺激だ。木漏れ日、水面の光、水玉模様などを見て発作を起こす人や、エスカレーターのしま模様、田んぼの落ち穂が苦手な人もいる。1997年、テレビアニメで光の点滅を見た子どもたちが相次いで救急搬送されたのも視覚刺激によるものだった。時間的あるいは空間的に繰り返す刺激に脳は敏感なのである。治療は生活指導だけで薬は不要なことが多い。
珍しいのは「読書てんかん」だ。ある患者は電車の中で本を開いた途端に倒れた。服薬で本を読めるようになったものの、年に数回は発作を起こす。理由は古本屋で長時間過ごすため。無類の本好きな彼の場合、生活指導は意味をなさない。
「お湯(ホットウオーター)てんかん」もある。インド南部ではバケツに入れたお湯を頭からかける風習があり、その都度倒れる症例が報告されている。恐らく強い皮膚感覚が脳の一部を刺激するのだろう。
私が診察したある患者は風呂場でいつも倒れていた。ところがよく話を聞くと、原因はお湯ではなく市松模様のタイルだった。無地のタイルに張り替えたら発作は止まった。この場合は「お湯てんかん」ではなく視覚過敏である。
冒頭で述べたとおり、てんかんには通常、誘因はない。危険因子としては極端な睡眠不足と飲酒ぐらいだ。外来で「発作は日々のストレスが原因ですか」とよく聞かれるが、ストレスに責任はない。「ストレスなしの人生なし」と答えている。てんかんがあろうがなかろうが、患者には人生の荒海を乗り越えてもらわなければならない。そのために専門医が必要なのだ。
第3回(2013年2月27日河北新報朝刊)てんかん新患外来/長時間の問診が大切
精神科医で作家の加賀乙彦に「ドストエフスキー」という作品がある。ある日、患者がこの本を持参して言った。「私の症状は全部ここにあります」。ドストエフスキーには側頭葉てんかんがあった。彼は自らの体験を基にして、小説の登場人物に恐怖や不安、焦燥感、非現実感といった奇妙な発作を語らせている。
てんかん発作は脳の部位ごとの働きを忠実に表現する鏡だ。音や光の異常知覚、恍惚(こうこつ)感、込み上げる上腹部の不快感など、その内容は実に奇妙で多彩である。一般の医師は、まさかこれがてんかん発作だとは思わないほどだ。
そこで専門医の出番となる。時間をかけて発作症状を聞き出す。てんかん科の新患外来では患者1人に最低1時間は費やす。脳波や画像の診断よりも、長時間の問診の方が大切だ。発作の種類によって使う薬も違う。話を聞いたら、てんかんとは別の病気だったこともある。
1時間外来はぜいたくだとの批判もあろう。決まった時間で診察できる患者数には限りがある。新患予約は3か月待ちだ。
でも、私は1時間外来をやめるつもりはない。10分で6人を診察するよりも、1人に1時間がよい。その患者を幸せにするだけではない。紹介状を詳しく書けば、かかりつけ医の勉強にもなる。その医師が将来、別の100人や1000人を助けてくれるだろう。全国で500人足らずの専門医が懸命に診療しても、100万人いるとされる患者全員をカバーすることは無理だ。それよりも、てんかん診療医の仲間を増やしたい。
そうして将来、もしも時間の余裕ができたなら、あの分厚い「カラマーゾフの兄弟」でも読んでみようか。
第2回(2013年2月20日河北新報朝刊)大学病院てんかん科/誤解や偏見 解消急務
東北大医学部の学生時代から脳と心に強い興味があった。脳神経外科の実習で見た先輩医師たちに一目ぼれして、入局を決意した。
最初に受け持った男性患者は側頭葉に血管奇形があった。彼はスキーのレース中、コースから外れてゆっくり下まで降りてくる事件を起こした。本人は何も覚えていない。側頭葉てんかんに代表的な無意識行動の発作だった。薬は効果がなかったが、血管奇形と脳の一部を取る手術で発作は消え、元通りの生活を取り戻すことができた。
それから紆余(うよ)曲折があったのだけれど、3年前、母校に日本初の「てんかん科」をつくることができたのは幸せだった。ところが「てんかん科」の看板を心配する人がいた。漢字の「癲癇」には「気が狂い、カッと興奮する」という意味があるからだ。妻は「患者さんは嫌がるんじゃないの?」と心配してくれた。「別の名前にしたら」と言う同僚医師もいた。
しかし、私は「てんかん」を使うことを譲らなかった。てんかんは多くの場合、薬や手術で発作を抑えることができ、普通の生活を送ることができる。決して差別や偏見の対象になるような病気ではないのだ。最新の診療法を一般の方にも医師にも、もっと広める必要がある。何よりも、てんかんへの誤解や偏見を取り除くことは急務だ。
新米医師だったころと同様に、今もてんかんの面白さにほれ込んでいる。奇妙な発作の原因となる脳の仕組みが面白いし、脳の一部を取ると発作が消えてしまう方もいる。患者と喜びを共有でき、一緒に泣いたりもする。私にとって、てんかんの4文字は「みかん」や「きんかん」「夏みかん」と同じぐらいにかわいくて、いとおしい。
第1回(2013年2月13日河北新報朝刊)てんかん学/先端研究 次々と成果
てんかんは言葉としてはよく知られているものの、多くの方に誤解されている疾患だ。知り合いの小児科医は「脳の不整脈」と説明しているそうだ。脳も心臓も電気のリズムを持っている。てんかんでは脳のリズムが乱れやすいのだ。
ヒトの大脳には100億個以上の神経細胞があり、互いにブレーキをかけあって、興奮しすぎないよう調整しあっている。ところが、何かの原因でブレーキが外れる。すると、多数の神経細胞が一斉に興奮する。これが「てんかん発作」だ。
てんかん発作の症状は、脳の興奮する部位によって千差万別だ。意識を失い手足をガクガク震わせる大きな発作以外に、数十秒間の動作停止や無意識行動の発作もある。意識は正常で、異常な感情や感覚に襲われるだけの数秒間の発作もある。てんかんは人口の1%が持つので、日本では100万人の病だ。また、赤ちゃんから高齢者まで何歳でも発症する。
治療法は日進月歩の勢いだ。多くの場合、薬で発作を抑え、普通の生活を取り戻すことができる。薬が駄目でも、手術で治る方は少なくない。 てんかんに関する最新情報を一般社会だけでなく、医師や医療従事者にどのように正しく伝えるかが私の最も重要な仕事だと考えている。てんかんを知ることは、脳の働きを理解することにもつながる。この連載では、てんかん診療と脳研究の話題を、なるべく分かりやすく紹介したいと思う。