日本てんかん学会東北地方会の第2代会長として,2016年1月1日付にて任期の二期目に入りました.ここに一言,ご挨拶申し上げます.
本会の歴史は1979年発足の「東北てんかんシンポジウム」に遡ることができます.名称は1982年に「東北てんかん研究会」,1988年に「東北てんかん学会」と改名され,毎年,東北6県の持ち回り開催によって年次大会を重ねてきました.日本てんかん学会の活動とは歩調を合わせつつも,独自に会員を募り,東北地方のてんかん診療の発展と普及に貢献してきました.その後,日本てんかん学会では地方会制度を発足させることになり,東北てんかん学会がその受け皿になることが決まりました.日本てんかん学会東北地方会の名称は2006年7月の総会より使われ始め,2006年9月に開催された日本てんかん学会の理事会および総会で正式な承認を受けております.初代会長の伊東宗行先生(社会福祉法人新生会みちのく療育園 園長)が2期6年を勤めたあとに勇退され,2013年より私が第2代会長を拝命しております.
東北は日本における「てんかん学」および「脳波学」の発祥の地として知られています.東北帝国大学生理学教室教授であり,のちに東北大学総長をつとめた本川弘一先生は戦前より脳波の研究に着手し,1952年には日本脳波学会を設立しました.本川弘一先生の教え子たちは,その後,東北地方のみならず全国各地で,てんかん学と脳波学の発展に尽くしてきました.さらに遡りますと,仙台医専校長をへて1916年に東北帝国医科大学の初代学長をつとめた山形仲藝先生は,日本で最初のてんかん外科治療(減圧開頭術)を行ったことで国際的にも知られております.
てんかん学会東北地方会が誕生後も,てんかん学と脳波学における会員の活躍には目覚ましいものがあります.福島県の幹事代表を務める丹羽真一先生は日本臨床神経生理学会の会長として,東北てんかん学会時代の会長をつとめた兼子直先生は日本てんかん学会の会長として,それぞれご活躍されました.一方で,専門医の偏在の問題や,専門治療を受ける機会が少ないといった問題が,東北地方におきましても未解決のまま残されています.このような中で,2011年3月11日,あの東日本大震災が発生しました.この時には,本会会員の結束力の強さが大いに発揮されたと思います.日本国内の支援団体と連携しつつ,被災地への直接の支援が,早い段階から組織的に展開されたことは,皆様の記憶にも新しいところです.震災で失ったものはあまりにも大きく,復興という言葉を軽々しく口にするのは憚られるのが現状ですが,この時代であるからこそ本会は会員相互の結束を益々強め,てんかん診療の理想郷を東北の地に作らなければなりません.
現在,日本のてんかん診療は新しい時代を迎えつつあります.2015年11月,厚生労働省は「てんかん地域診療連携体制整備事業」をスタートさせ,2016年4月の診療報酬改定では,長期間脳波ビデオ同時記録検査の大幅増点など,てんかん診療に関連する項目の積極的な見直しが行われています.私達は東北地方の診療連携モデルの良さを全国に波及させるべく,これまで以上に結束を固めて活動を展開したいと存じます.会員諸氏の益々のご協力をお願いして,ご挨拶とさせていただきます.
2016年1月吉日
日本てんかん学会 東北地方会 会長
東北大学大学院医学系研究科てんかん学分野 教授 中里 信和
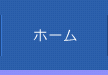

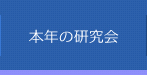
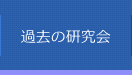

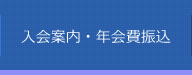



 日本てんかん学会
日本てんかん学会 国際てんかん連盟
国際てんかん連盟